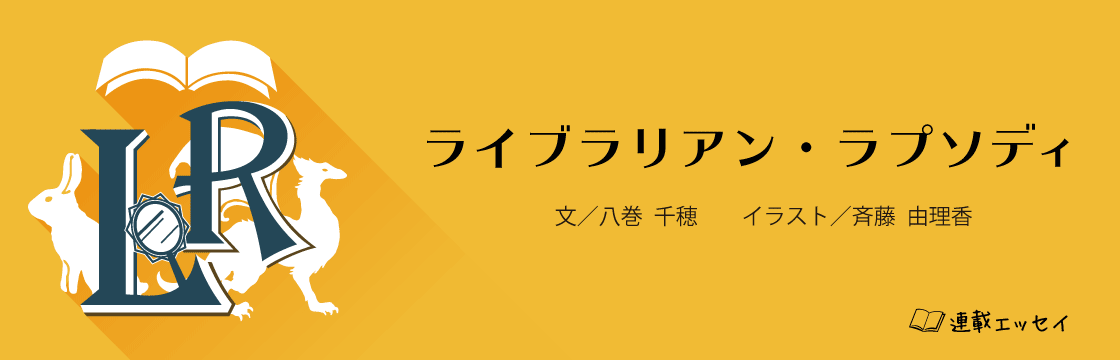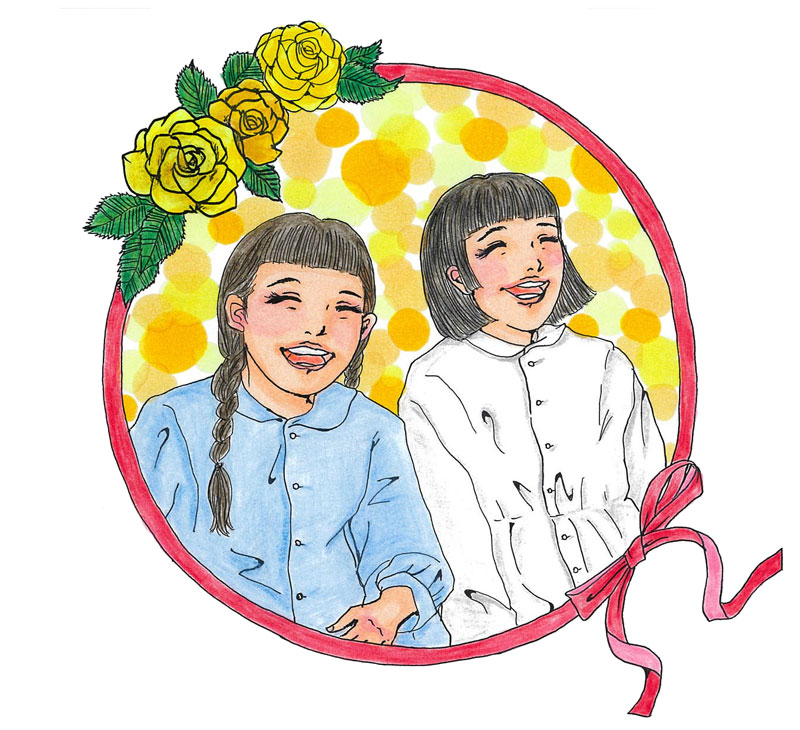(株)郵研社ホームページへようこそ
郵研社
52 愛、発見!?
「家族経営論」なる授業だったと思う。結婚、離婚について考察するという課題に取り組んだときのこと。白紙にタテヨコ1本ずつ線を引き、4つの枠をつくり、枠内に結婚・離婚のメリットとデメリットを箇条書きするというもの。作業後、さぁ検証だぁ!と、手をとめて枠内の項目をしばし眺める。と、右上の枠と左下の枠の書き込みが圧倒的に多いことに気付く。ん?つまり、結婚のデメリットと離婚のメリットについての書込みが多かったのだ。当時まだ10代、もちろん結婚の経験はない。しかし、すでに結婚に対する負のイメージと、離婚によるポジティブなイメージが形成されていた。
結婚が沼地のように女性のすべてを窒息させるような息苦しい感覚、一方離婚が自身を生きるための自由へのチケットかのような解放感と高揚感。頭で考えるというよりも身体的感覚に近いかも。んー、これっていったい?前世で何かあったの・・・か?
NHKプレミアムドラマ「団地のふたり」を見ながら、ふっと思い出した「家族経営論」の一幕。このドラマは、芥川賞作家である藤野千夜の『団地のふたり』(双葉文庫,2024)が原作となっている。50代、独身、同じ団地の実家に住む幼なじみのノエチと奈津子。互いの人生のいいときも悪いときも知っているし、お互いの良いところも悪いところも熟知しているし、自分がどんな人間かをわざわざ話す必要なんてない関係。家族じゃないけど、家族のような存在。なんだかいいなぁ、ホッとするよ。そして‘頑張って’友だちをしていない!というところがとっても心地いい。夫婦もこうだったらね、だけど恋愛にも家族(夫婦)にも‘経営’がともなうから、過度の期待をしちゃうのかも。
『世界は経営でできている』(講談社現代新書,2024)によると,家族(夫婦)も恋愛も経営でできているとある。夫婦の場合、相手に価値を提供すべく主体的に問題解決していかなればならないはずが、夫の失態は「夫になった瞬間に、まるで母からみた子のように、夫は赤ちゃんぶって自分の存在そのものが妻への価値提供になっていると思いたがっている」と。また恋愛における経営の間違いは、目的に対して過大な手段の罠、目的と手段の転倒の罠、短期志向と近視眼の罠が潜んでいると。恋愛は手段であって、その先にある自分と相手の幸せという目的があるはずなのにね。と、「心労」、「健康」、「孤独」など様々な経営について書かれているが、ここには「友情」については登場しない。経営の枠外にある友情は希望となるか、はたまた友情は経営に値するものとは認識されていないのか。
「私たちの人生で友情ほど過小評価されている人間関係はない…法的にあるいは血縁や金銭でつながることのない関係だけれど、愛という暗黙の了解でつながっている」とは、日系米国人作家のハニヤ・ヤナギハラの言葉(『女友達ってむずかしい?』より)。そうでしょうとも!
また友達づきあいは血圧を下げ、体重が増えるのを防ぎ、免疫力を上げる、また心疾患から守り、風邪をひきづらくすると。さらに、ストレスレベルを下げ、気分をよくし笑わせてくれ、誰もが望む幸福感をもたらし身体的な痛みを和らげるエンドルフィンを分泌させるのだとも。様々なデータからの貴重な情報が『女友達ってむずかしい?』(河出書房新社, 2024)には書かれている。友達がいれば医者いらずってことかしら!?また、長年女性の友情について調査してきた進化人類学者であるアンナ・マシャン博士によると、異性愛者の女性は、恋愛対象の男性を含めた誰よりも、女性の友達に対して感情面で親密さを感じやすく、自分自身をさらけだしやすく、共通点を持ちやすいと。この発見には、博士もびっくりだったそう。
経営ってそもそもストレスなのよ。だから経営から解放された女性同士の友情ってとっても自由で貴重なんだ!『女友達ってむずかしい?』の著者が言うように、女性同士の友情は、人生における愛なのだ‼
design pondt.com テンプレート