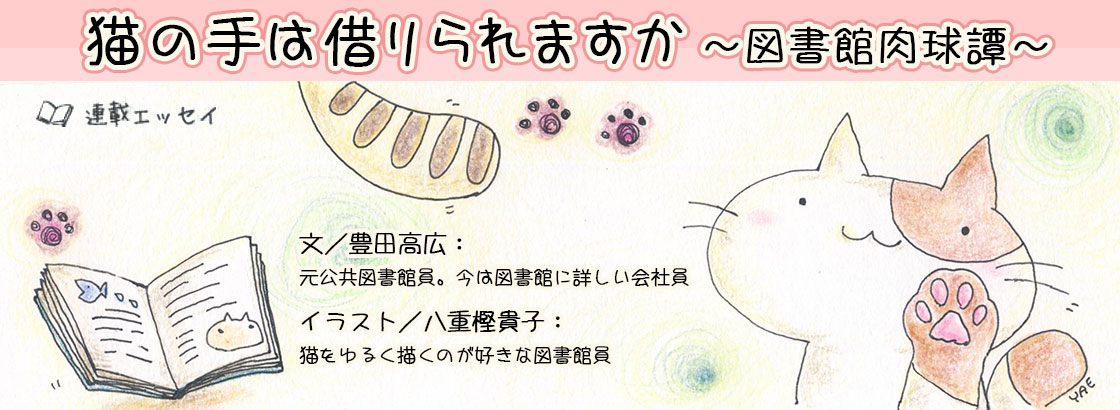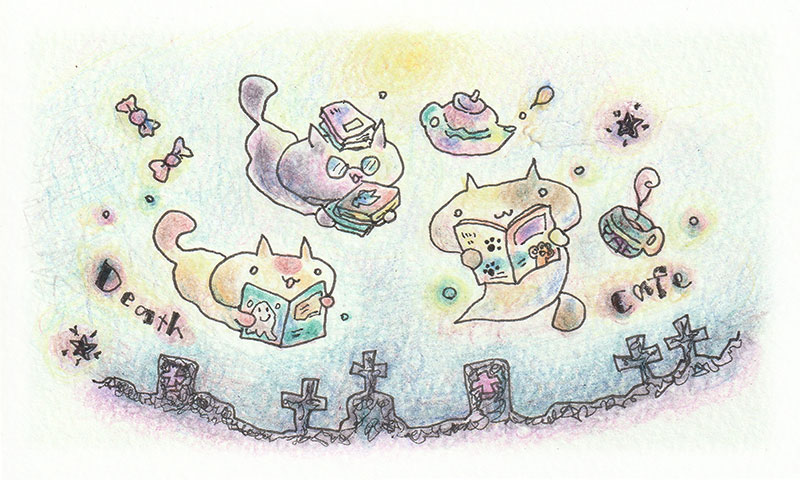(株)郵研社ホームページへようこそ
郵研社
第58回 図書館で”死"をカジュアルに語り合う
<デスカフェとは、「死」をタブー視せずに受け入れ、語り合う場です。>これは『デスカフェ・ガイド』にある言葉です(吉川直人他著、クオリティケア刊)。1年前の本コラムに、図書館でデスカフェをしたいと書いたところ、かつての勤め先、田原市図書館で実現しました。「デスカフェ」という名前ではありませんけどね。
昨年の10月、田原市図書館が開催した「対話ファシリテーター養成講座」(第52回参照)で「そもそも死の不安とは」という問いを対話によって掘り下げました。講師は哲学者の岩内章太郎氏。20人以上の参加者とともに、私もこの議論に加わりました。言わば、これが「デスカフェ@田原」の前半です。
12月には、同じく田原市図書館の主催で「ふしぎ文学半島プロジェクト2025 ふしぎシンポジウム」が、座談会形式で開催されました。テーマは、「 『死』って何だろう?」私の見立てでは、これが「デスカフェ@田原」の後半です。
パネリストは岩内氏に加え、妖怪文化研究家で生物教師・防災士の顔ももつ島田尚幸さんと地元民話の語り継ぎをライフワークにされている内浦由美さん、そして私の四人です。島田さんと内浦さんは、2012年のプロジェクト開始以来の心強い協力者でもあります。田原市は人口6万人に満たない町ですが、約90人が参加される盛況ぶりでした。タレント的な有名人をお呼びしたわけではないのに、人数の多さといい、アットホームな雰囲気といい、実に異例でした。
「参加者はみんな高齢では?」と思われるかもしれませんが、中には十代の方も数人いて、世代を問わず”死”をめぐって語り合える場が求められていると確信しました。テーマに関するオススメ本をパネリスト自ら紹介する時間があり、展示されている本の写真を撮る方が多いのも印象的でした。この催しに先立って、死をテーマにした本の期間限定コーナーが中央図書館内に設けられたのですが、担当者も驚くほどよく借りられたそうです。個人的には、終了後、複数の参加者からFacebookの友達申請をいただいたのにもびっくりしました。
「異例」と書きましたが、田原市図書館には「異例」を可能にする土壌があります。対話ファシリテーター養成講座や、ふしぎ文学半島プロジェクトに限らず、この図書館で行われる大小さまざまな出会いや対話の場がそれです。なかでも重要なのは、NPOたはら広場が月1回、中央図書館の館長室で開催している「おおきなかぶ会議」でしょう。文字通り誰でも参加できる、Zoomと対面のハイブリッドで出入り自由のゆるやかな会議体が、2011年以降、ほとんど休みなく続いているのです。もちろん、中央図書館長は必ず出席します。図書館で開催されるイベントの多くはこの会議への「持ち込み企画」であり、さまざまな市民と図書館の協働による事業です。こうした、軽いノリで参加できる「弱いつながり」が、田原市図書館の多彩な活動を支えているのです。
大きな予算や労力をかけるのが難しくても、関係者のオープンな姿勢とみんなの知恵(集合知)によって、市民の知的好奇心と学ぶ意欲に応える事業を実現していくのが公共図書館というものです。誰の人生にも平等に降りかかる”死”という課題についてカジュアルに語り合う場と資料を提供できるのは、理想的な「課題解決型図書館」のあり方かもしれません。
まずは、小さい一歩から。たとえば、”死”をテーマにした絵本の読書会とか。図書館の外でそんなことをしかけている人がいたら、声をかけてみましょう。「図書館でやってみませんか?」ぜひ、お試しあれ。