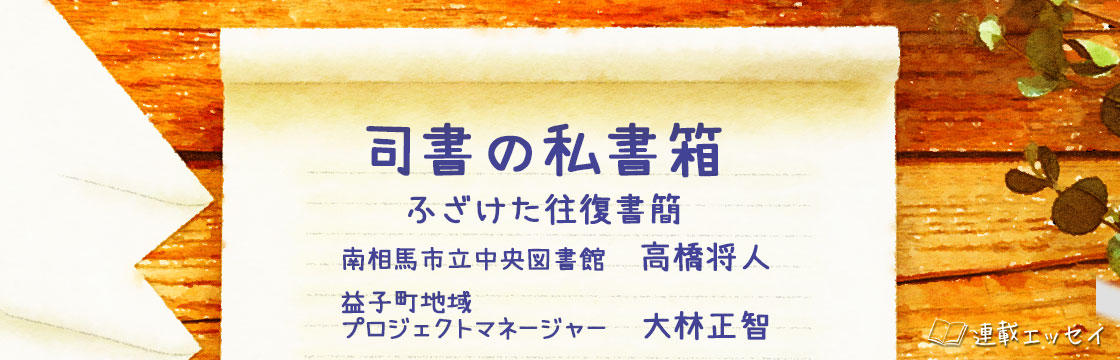(株)郵研社ホームページへようこそ
郵研社
No.36「鳥と左手の手紙」
こんにちは。年度が替わる頃はなんだかあわただしくて、ぢっと手を見る時間すらも惜しい、または捻出できない、なんてことはないですよね。いかがお過ごしでしょうか。
石川啄木。私、生まれて初めて買った歌集は『一握の砂・悲しき玩具』(新潮文庫)です。40年以上前、まだ「中二病」なる言葉もなかった時代ですが、今になって考えるとちょっとそれっぽい。「空に吸はれし十五の心」なんて、「うわー」って(他に表現しようがないんです)思いましたよ。「我を愛する歌」ですもんね。自己愛というか自己憐憫というか、とにかく「うわー」です。
尊敬はできないけれど憎めない、という私のなかの啄木像は関川夏央、谷口ジロー『坊ちゃんの時代 第三部 かの蒼空に』(双葉社 1992)によって形成されたところが大きいです。シリーズの他の作品もおもしろいので、もし未読でしたらどうぞ。
啄木というのが「キツツキ」のことだというのは、どこで知ったのだったか。これをペンネームにしたというのが啄木らしいというか、このペンネームに吸い寄せられるようにコツコツコツコツと歌を詠みつづけることになったのか。
キツツキが木を啄むのはコミュニケーションのためだということです。そう思うとペンネームがいっそう意味ありげに見えてきますね。
鳥といえば、近所の公園でカワセミを見るのが最近の楽しみになっています。自然の中で鮮やかな青い色が視界に入ると反射的にハッとしますよ。またマガモ、カルガモなどの水鳥を見るのも好きです。長新太『トリとボク』(あかね書房 1985)を思い出しますね。
鳥の話になってしまいましたが、啄木の「ぢっと手を見る」でした。ぢっと見た手は片手なのか両手なのか。さて、と思い私も手を見てみたんです。両手をぢっと見るのは難しいと思いました。右と左とに視点が揺れてしまって「ぢっと」見ている感じにならないんです。ですので私の解釈&想像も片手、ということになります。
さらに左右ですが、「ふと」見るのは、利き手でないほうの手なのかな、と。右利きであれば、右手には何かを持っていることが多い。筆記用具であるとか、包丁であるとか、農具であるとか。だとすると「ふと」目をやって「ぢっと」見てしまうのは、空いている手なのではないか、というのが私の推論です。
『SLAM DUNK』(スラムダンク)(井上雄彦 集英社 1990~1996)というバスケットボールマンガの金字塔作品に「左手はそえるだけ」という名台詞があります。シュートのフォームについて言っているんですが、たしかにバスケットボールのシュートの基本は(右利きなら)右手でボールを送り出し、左手は「そえるだけ」。ただ「そえるだけ」ではあるけれど、そえないとだめなんですよね。その微妙なところがおもしろい。
文字を書くときも左手はそえています。メモ書きとか、ちょっとした分量なら右手だけでも書けないことはないんですが、手紙のようなものとなると、やはり左手をそえて書きたいですね。また、かしこまった文章は(手書きでなく、PCを使うにしても)足を組んで書くことはできないような気がします。PCでも、気持ち的には「左手をそえて」書いているのかもしれません。飯舘村の「までい」ですね。本当に大切なのは、実際に両手ですることではなく、気持ちが「までい」であることなのでしょう。
それはそうと、私たちは「読む」という行為についてよく話すし、考えますけど「書く」についてもそうしたら楽しそうだな、と思ったことでした。(大)