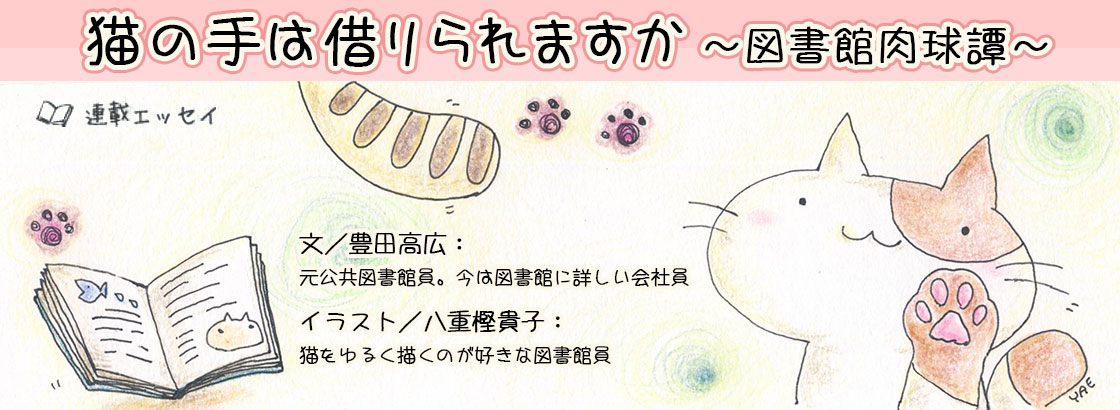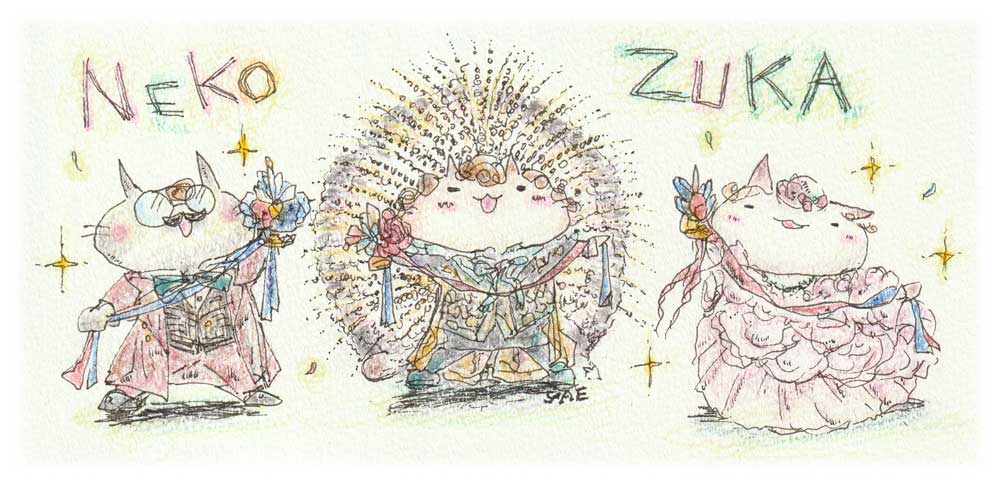(株)郵研社ホームページへようこそ
郵研社
第47回 大階段で図書館が変わる
二十年以上前、宝塚歌劇を初めて観ました。勤め先の図書館員の一人が宝塚歌劇のファンで、職場内でツアーを組んでくれたのです。劇場に入れば、そこは異世界。中でも私を魅惑したのは、ステージ上の大階段を使ったきらびやかなフィナーレでした。
<大階段は「おおかいだん」と読み、宝塚大劇場や東京宝塚劇場で使われる、宝塚歌劇独自の舞台装置です。出演者が大階段を華やかに降りてくるフィナーレを楽しみにされている方も多いのではないでしょうか。>(Facebookの宝塚歌劇公式ページより)
四半世紀後の自分が「大階段」じかけの図書館(それも複数!)の開設にかかわるようになるとは、思いもよらないことでした。
図書館インテリアの最大の特徴である書棚は、図書館家具としては「書架」と呼ぶのが一般的です。とりわけ人気があるのが、頭上まで本で人を取り囲むようにそびえ立つ書架。図書館建築に携わる人々の間でも、知的な雰囲気を醸し出すにはうってつけと思われてきたようです。しかしながら見方によっては威圧的で、私も息苦しさを覚えることがありました。だからこそ、図書館の真ん中に大階段を置く建築が登場し始めたとき、私に違和感はなく、むしろ大歓迎だったのです。
計画段階で私が関わった図書館のうち、大階段があるのは2021年11月に開館した豊橋市まちなか図書館と、その翌年4月に開館した鹿児島市立天文館図書館です。どちらの計画も、地方都市の中心市街地ににぎわいを取り戻す戦略の一環でした。
両館とも、大階段は上下二つのフロアをつなぐ通路であると同時に、階段を降りた先にあるスペースで繰り広げられるイベントを眺める座席でもあります。イベントがないときも、多くの人々が階段に腰掛け、読書や会話を楽しんでいます。その横を昇り降りする人もいる光景は、まさに「広場」です。
古今東西、まちに暮らす人々が触れ合い、自然に会話と対話、議論と世論が生まれる場所が、広場でした。広場に集まる人々の出会いがきっかけとなって、集会でまちの課題を議論し、祭礼でまちの記憶を受け継いだものです。民主的な社会には欠かせない装置であるはずですが、近代日本の都市にはなかなか育ちませんでした。
三十年以上前、公共図書館を「本のある広場」にしよう、と主張した図書館員がいましたが、当時、この考えを支持する人は少なかったようです。
<「本のある広場」は図書館そのものであり、「本との出会い 人との出会い」というのがその内容となる。広場は自由であり、いろいろに展開される可能性をもっている。…私の考えでは、ひろばは集会機能を含むもので、住民主体の考えといえよう。>ちばおさむ『本のある広場:ある下町の図書館長の記録』教育史料出版会刊
ところが、今、各地の図書館に拡がりつつある大階段は、異なるジャンルの知が広がるフロア同士をつなぎ、多様な属性の人々が交わる、知の広場となっているのです。私が夢見るのは、図書館の大階段が、通路であり、客席であるだけでなく、舞台にもなることです。そう、宝塚歌劇の大階段のように。
大階段にかぎらず、図書館を「本のある広場」にする手立てはいろいろあるはずです。劇場のホワイエ、旅先のオープン・カフェ、縁日の露店など、あなた自身の経験を振り返って広場の記憶を甦らせるところから始めてはいかがでしょう。ぜひ、お試しあれ。