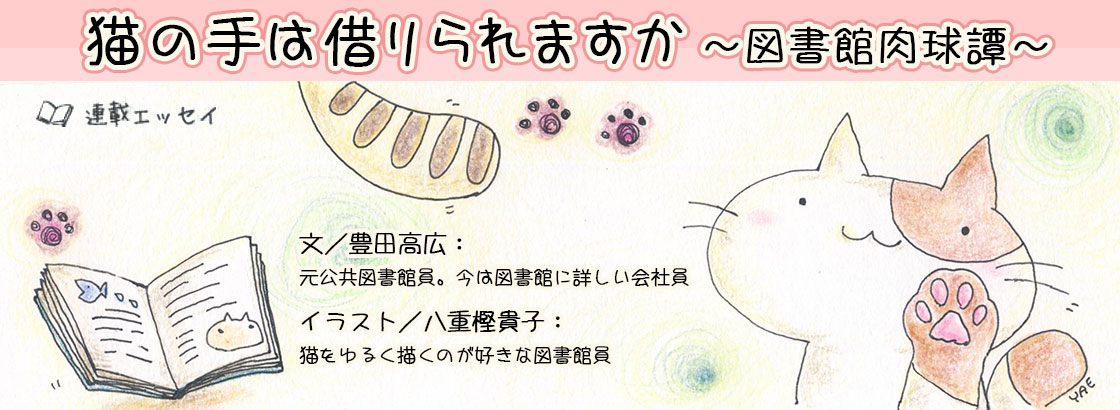(株)郵研社ホームページへようこそ
郵研社
第46回 図書館にデスカフェを
新しく開館する図書館にカフェを併設する動きは珍しくありません。でも、それは建築の話。私に興味があるのはカフェの使い方、すなわちカフェ文化です。
損得勘定や世間体を気にせずに誰でも参加し、飲み物とお菓子をお供に寛いで会話を繰り広げるカフェ文化に憧れます。精神科医の名越康文氏は著書『驚く力』(夜間飛行)で、トルコの喫茶文化(ラーハ)を「目的のない世間話」、「豊かな知的無駄話を楽しむ時間」と評していますが、まさにそんなイメージです。タイパ・コスパ重視の風潮に逆らうようですが、今の時代にはそういう時間が少なすぎるのではありませんか。
日本の図書館ではサイエンスカフェや認知症カフェが行われるようになりましたが、私が取り組みたいのは「デスカフェ」です。死を過度に恐れ、忌み嫌うかぎり、私たちは幸福になれないと、コロナ禍のおかげで気がついたので。
<デスカフェとは、「死」をタブー視せずに受け入れ、語り合う場です。宗教、国籍、年齢、性別等に関係なく、お茶やコーヒーを飲みながら語り合うことで終末期、看取り、近親者の死という経験を抱えた者、当事者、死について学びたい者などが分け隔てなく繋がる場です。>吉川直人他『デスカフェ・ガイド』クオリティケア刊
2024年の夏から秋にかけて、NVC(Non Violent Communicationの略。第25回参照)を共に学ぶ仲間と、主にオンラインでデスカフェ的な場づくりを試しました。週1回、早朝の1時間を使って、自分自身や親しい人の弔辞をつくって読み合ったり、「414(よいし)カード」というツールを使って各自の死生観に関する問いに交替で答えてみたり。
私はこの活動の中で、「こんな死後は嫌だ」というイメージを、落語「死神」の続きという体裁の一人芝居にまとめ、数十人を前にして演じることができました。死への思いを表現し、自分以外の人たちに笑いながら受け取ってもらえたのは、予想以上にうれしい経験でした。中世ヨーロッパで流行したという「死の舞踏」も、いつか自分なりに表現してみたいものです。
今、私は地元の図書館でデスカフェを開催することを画策しています。かつての職場を拠点として地元の人間関係を再構築したいという個人的な事情以外に、あえて図書館でやりたい主な理由はふたつです。
第一に、図書館はその蔵書も、集まる人もきわめて多様であること。あらゆるジャンルにかかわり、あらゆる人が無関心ではいられない「死」というテーマを扱う対話の場にふさわしいのです。
第二に、図書館は不特定多数の人が行き交う広場のような空間ですが、そこから新しいコミュニティが生まれるしかけについては、大いに開拓の余地があることです。それは公民館の役割だ、という声が聞こえてきそうですが、広場的機能を発揮できている公民館がどれだけあるでしょうか。コロナ禍以降、人と人が対面でつながる機会がますます減り、コミュニティの解体と人々の孤独化は地域社会の最大の問題といってよいでしょう。公民館も図書館もそれぞれの得意を活かし、手を取り合って取り組むべきです。
あなたの図書館の利用者の中にも「デスカフェ、やってみたい」という方はいるはず。ミニ展示でもミニイベントでも、取り組みやすいところから一歩目を踏み出してみてはいかがでしょうか。ぜひ、お試しあれ。