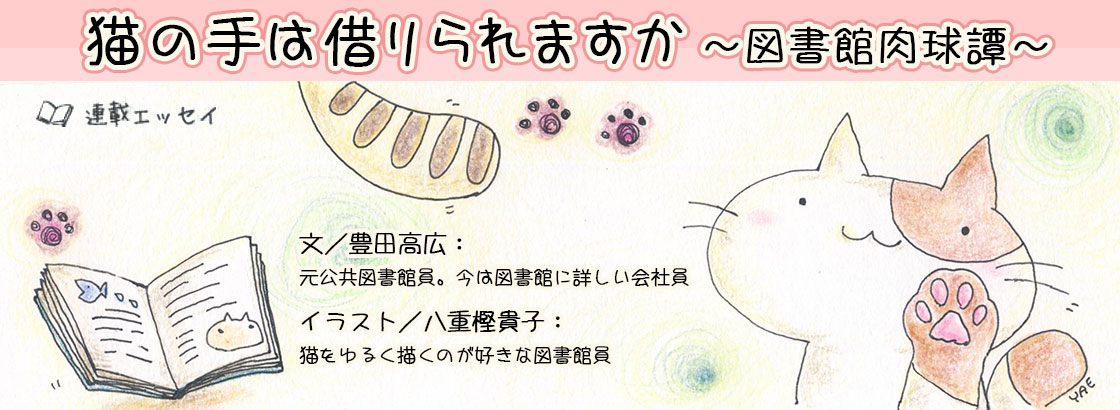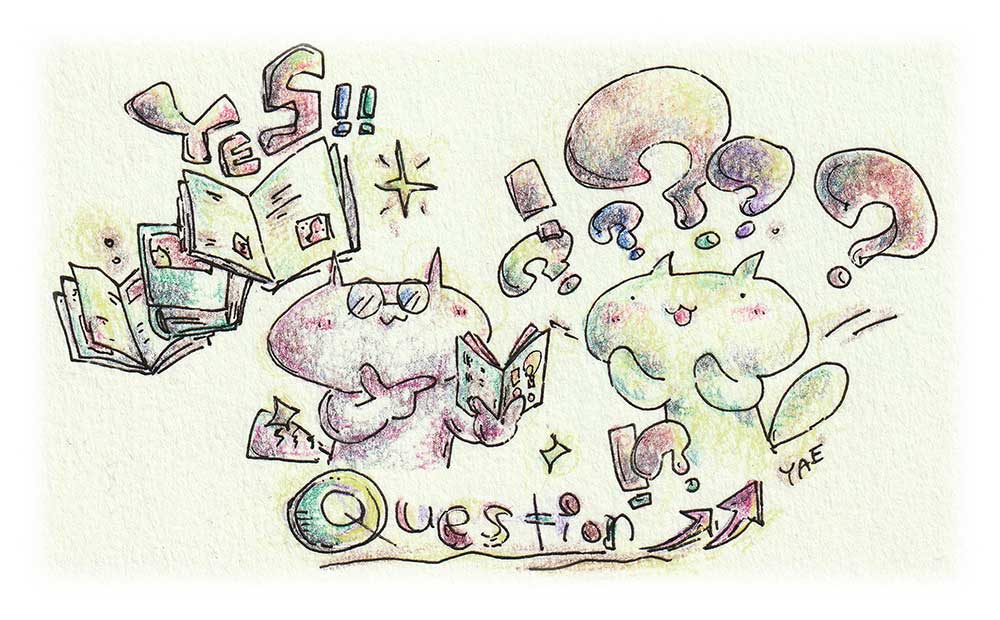(株)郵研社ホームページへようこそ
郵研社
第32回 問いは怖いか、楽しいか
小学校に上がる前の子どもは、次々と問いを発する「問い生成マシン」です。なぜ、あんなに質問するのか分かりますか?私が思うに、一つは、疑問が解決することの気持ちよさ。もう一つは、やりとりを通じて相手との関係が深まることの楽しさ。そこにあるのは、対等のパートナーシップ的関係です。
しかし、学校の生徒ともなれば、質問は教師の特権になります。生徒が質問するのは分からないから。分からないのは能力が不足しているから。したがって、生徒が質問するのは自分の無能の証明。こうして、問いは怖いものになるのです。子どもたちが系統的かつ効率的に知識を得ることができる学校制度の、ちょっとした副作用…そう言い切ってしまっていいのでしょうか?
こうして私たちは、質問できない大人になりました。「そんなことが分からないのか?」「質問していいか悪いか、空気を読めよ。」こんな声を、すっかり内面化してしまった私たちは、学校を出てからも、繰り返しこの“学習”を強化し続けています。
現代日本の学校には、こういう状況を変えようと努力している教師が大勢います。でも、大学や研修で教える立場に立つと分かるのです。やはり、教わる側にとって質問するのは怖いことらしい。実は私自身も、質問するときは自分が賢くみえるように、そして、誰かの機嫌を損ねないように、ばかばかしいくらい念入りな注意を払っています。もちろん、知らず知らずのうちに。
だからこそ、学校とは異なり、知識に自由気ままなアクセスができる図書館というしくみが、問う楽しさを取り戻すのに一役買えないか?そんな風に思うのです。
戦後の日本において、レファレンス・サービスは図書館サービスの二本柱の一つといわれてきました。しかし、普段このサービスを利用するのは数人の常連だけ、といった図書館現場の悩みもよく聞きます。自由に問うことを楽しむ人抜きでは、成立しないサービスですからね。では、問うことを楽しくするにはどうすればいいか。まさに、そんな問いを立てることで、日本の図書館サービスは飛躍のチャンスをつかむかもしれません。
司書猫たちのイラストを描いてくれている現役司書の八重樫貴子さんに、今回は以上のようなことを書きたいと伝えました。すると、「対話型AIに問う力を試され、鍛えられ…今後コラボしてお互い相乗効果が生まれる…?!」というメモが返ってきたのです。たしかに、対話型人工知能の登場で、あらためて問う力が試されていますね。
たとえば、司書とAIが競って利用者の質問に答える、そんなイベントをやってみてはどうでしょう。利用者の中から「答えたい人」が飛び入り参加するのも大歓迎。夏休みの自由研究に欠かせないオリジナルの「問い」を考える講座もできるかな?「どうしたら問いを“怖い”から“楽しい”に変えられるか」という問いから、多彩なプログラムが生まれそうです。レファレンス・サービスの不振に悩む司書猫のみなさん、ぜひ、お試しあれ。