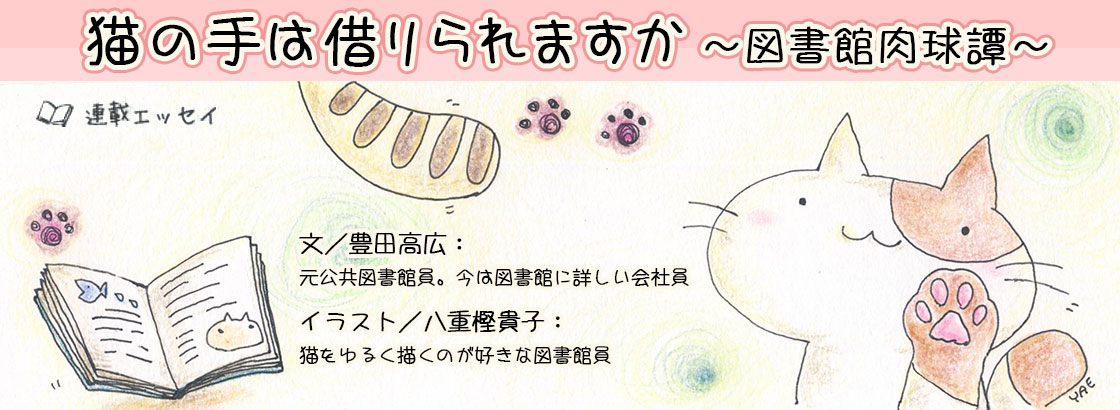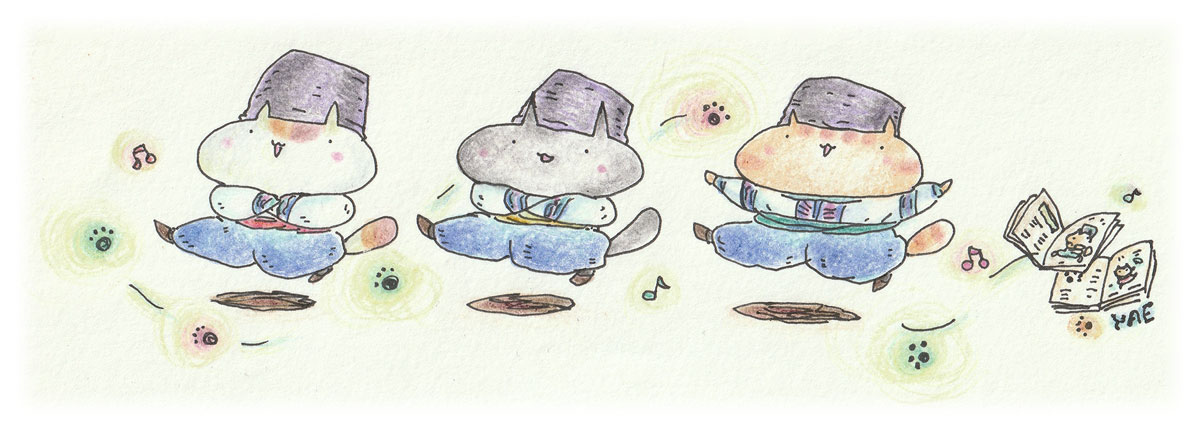(株)郵研社ホームページへようこそ
郵研社
第13回 戦争だから世界文学でも並べようか
3月のある日の朝。いつものように新聞をめくると、ウクライナに住むという小説家の寄稿が目にとまりました。
<人間には希望が必要だ。希望無しでは、人生は灰色で平凡になる。まるで(ウクライナ東部の)ドンバス地方に定められたロシア軍とウクライナ軍の間の「グレーゾーン」(両国どちらの占領地でもない場所)のように。>アンドレイ・クルコフ「ウクライナ 戦下の叫び」(沼野恭子翻訳監修 朝日新聞2022年3月16日朝刊)
敵味方に分かれた陣営のどちら側にも人間がいます。しかし、戦争となれば指導者は天使か悪魔、一般兵士や非戦闘員は数値と見なされるでしょう。希望と共に色彩も失われ、何もかもが灰色のグラデーションになってしまいます。戦争はグレーゾーン、すなわち国境地帯をどこまでも拡大する運動と言えるかもしれません。でも、人間を抽象的な観念や単なる数値として扱うことを、断固として拒否する言葉があります。文学です。
この寄稿を読んでロシアとウクライナの人々が登場する本が無性に読みたくなったので、近所の市立図書館に出かけました。借りたのは、ウクライナの首都キエフ(又は“キーウ”)を舞台にした、クルコフとブルガーコフの小説。それから、NHKの「100分de名著」で紹介されていたノンフィクション作家アレクシエーヴィチのインタビューや講演を収めた本。ついでに、ロシア文学にしばしば登場し、ウクライナの歴史でも重要な役割を演じてきたコサックと呼ばれる人々を描いた歴史書も。
久々に海外の小説を読むうちに思い出しました。私は物心ついた頃から外国の話が好きで、学校図書館にあった子供向けの世界文学全集を片っ端から読みまくったものです。中学に入ると、できたばかりの市立図書館にでかけて大人向けの棚を物色しました。島国の地方都市での暮らしを息苦しく感じ始めた思春期の私にとって、世界文学は「今・ここ」を別の時空間につなぐ風穴のようなものだったのです。
翻訳物は読みにくい、だから読みたくないという声を聞くことがあります。もったいない話です。どんな本だって読み手を別世界に連れていく扉になり得ますが、その中でも翻訳は、途中の駅を飛ばしてまっしぐらに扉の向こうへ連れて行く特急列車のようなものなんですから。
読書は文学に限る、とは思いません。ジャンルを問わず、読みたいときに読みたいものを読むのが読書の王道です。でも、戦争が身近に感じられるときには、多様な人間の生き方と世界のあり方を映した、カラフルで、矛盾だらけで、それだからこそ魅力を放つ海外の文学を多くの人に読んでほしい。ロシアやウクライナの文学に限定する必要はないんです。たとえば「はじめての人のための世界文学」といったテーマで本を展示し、ブックリストを配る。対面でもリモートでもよいので、読書会のようなちょっとしたイベントをしかける。それは図書館にふさわしい仕事ですよね。世界中が国境地帯に変わってしまう前に、お試しあれ。